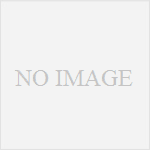
パールホワイトプロEXプラス: 歯の美白と健康を一緒に叶えるオールインワンケア
パールホワイトプロEXプラスは、薬局やドラッグストアで手に入らず、市販されていない商品ですが、通販サイトや公式サイトから手軽に購入でき、楽天...
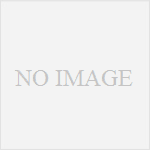
パールホワイトプロEXプラスは、薬局やドラッグストアで手に入らず、市販されていない商品ですが、通販サイトや公式サイトから手軽に購入でき、楽天...
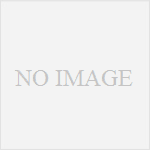
お腹がすいた時、愛犬にも美味しく安心な食事を提供したいと思いませんか?ブッチドッグフードは、選び抜かれた原材料で作られ、その食いつき...
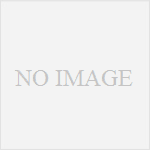
ドッグフードの選び方は、愛犬の健康と幸福に直結する重要な決断です。以下に、ドッグフードを選ぶ際に考慮すべきポイントを紹介します。 まず...
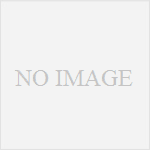
お気に入りのトートバッグを長く美しく保つためには、定期的なクリーニングと適切なメンテナンスが欠かせません。汚れや傷が気になる前に、正...
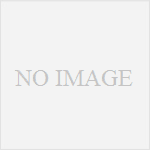
自信を持って輝く女性は、魅力的で影響力を持つことができます。その一環として、良好なコミュニケーションスキルは不可欠です。自信を持って他人とコ...
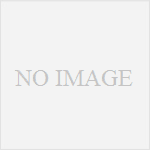
小顔用のコスメは、各種発売されていますし、クリーム等も販売されています。小顔になるためには、毎日行うこと、そして自宅で手軽に続けられることが...